-

内藤明著『抒情の構造 ―喪われた〈故郷〉の位相』
¥4,180
近代短歌は、万葉集をはじめとする歌の古層から、喪われた〈故郷〉を幻視する術を継承した。だが、〈故郷〉があったことさえ忘却された今日、始原への憧憬が、鉄幹、晶子、子規、左千夫、茂吉、白秋、空穂、御風、牧水、また武川忠一、上田三四二、玉城徹、山崎方代らにおける〈故郷〉の位相を読み解くことへと著者を向かわせた。『万葉集の古代と近代』に続く労作。 世界の秩序が音を立てて崩壊していく様を、われわれは目の当たりにしている。(略)あらゆる境界が失われ、内部も外部も混沌とした現在、人間と自然の一体といった認識は、神話であるとともに現実でもある。壊れ浮遊しつつ、自然に包摂されていく主体から発せられる、現代の絶望と祈りが一体となった歌を、私は夢想するのである。[本書より] 本書の内容 序 絶望と祈り Ⅰ 万葉集とうたの生成 第1節 祈りと再生―『万葉集』天智天皇挽歌群を素材として 第2節 抒情の構造―始原への憧憬 第3節 季節の叙景―人麻呂歌集宇治河作歌二首をめぐって 第4節 漂泊・叙景・抒情―高市黒人と山部赤人 第5節 表現としての恋―坂上郎女 第6節 老いと人生―旅人と憶良 第7節 規範性からの逸脱―東歌をめぐって 第8節 『万葉集』に鳴く鳥 第9節 根源へむかうもの―五つの元素と歌 Ⅱ 近代短歌の成立 第10節 〈近代化〉と〈短歌〉 第11節 〈われ〉の生成・主体のゆくえ 第12節 和歌・短歌の音楽性 第13節 与謝野鉄幹覚書 第14節 与謝野晶子の春 第15節 晶子の熟成―『舞姫』と『夢之華』 第16節 晶子晩年の一首 第17節 正岡子規―継承と創造 第18節 伊藤左千夫―「おりたちて」の意味するもの 第19節 斎藤茂吉『赤光』と『万葉集』―原郷の彼方へ 第20節 茂吉の戦中歌集 第21節 北原白秋『雲母集』と『梁塵秘抄』―「赤」への傾倒 第22節 窪田空穂―〈実感〉への信頼 第23節 空穂と『万葉集』 第24節 相馬御風―飛翔と回帰 第25節 若山牧水の〈自然〉 Ⅲ 武川忠一と戦後の時間 第26節 歴史と時間―古代の歌などをめぐって 第27節 現実と源泉と―歌論家・批評家としての武川忠一 第28節 風土の生成―武川忠一『氷湖』をめぐって 第29節 「ひかり」への憧憬―上田三四二小論 第30節 表現主体の影―玉城徹『樛木』寸感 第31節 重層化する〈私〉 ―「方代」と「われ」 第32節 記憶と詩―山崎方代『迦葉』 終章 第33節 故郷のありど 第34節 喪失と郷愁 定価:4180円(税込) 判型:四六判ハードカバー 頁数:434頁 ISBN:978-4-86534-477-6 初版:2024年3月31日 発行:現代短歌社 発売:三本木書院(gift10叢書第55篇)
-

江田浩司著『前衛短歌論新攷 言葉のリアリティーを求めて』
¥3,960
写生と反写生という二項対立の図式は、空疎な主導権争いを生んできた。そう考える著者はこの相克に終止符を打つべく、塚本邦雄、岡井隆、山中智恵子、浜田到、玉城徹らの作品に具現化した言葉のリアリティーを、周到に読み解いてゆく。真のリアリズムを求めて疾走する、スリリングな1000枚。 「私は葛原妙子の歌の世界を純粋に楽しむことができますが、山中智恵子の歌ではそれができません。山中の歌が内包する虚無が、歌を楽しむことへの脱臼を図るのです。(略)どちらかの歌を一つ選べと言われた場合には、私は迷うことなく山中の歌を選びます。それは、山中の歌が私にとっての「前衛短歌」であり、葛原の歌はそうではないということです。」(本書より) 本書の内容 はじめに 過剰さについて 第一章 岡井隆論 Ⅰ 原発と前衛 Ⅱ 岡井隆はなぜ詩を書くのか Ⅲ 「詩とは何か」に答えて Ⅳ 〈持続する書きもの〉をめぐって ――『注解するもの、翻訳するもの』を読む Ⅴ 共同詩の現場 ――創作に更新をもたらす他者 Ⅵ 詩人の首を飾る歌人 ――歌集『土地よ、痛みを負え』再読 Ⅶ 中断と注解 Ⅷ 『神の仕事場』から『静かな生活』へ ――「未来」創刊60周年記念大会の報告といくつかの感想 Ⅸ 詩作と思索 ――『詩歌の岸辺で』書評 Ⅹ 文学としての短歌の危機を生きる ――歌集『銀色の馬の鬣』書評 Ⅺ 虚無からの使者 ――歌集『鉄の蜜蜂』書評 Ⅻ 蒼白の馬との遭遇――哀悼 岡井隆 第二章 山中智恵子論 Ⅰ 「鬼のよはひ」を共に生きた歌人 ――前川佐美雄と山中智恵子 Ⅱ 破調と両性具有 ――未刊歌集『青扇』を中心に Ⅲ 短歌の全体性回復への希求 ――ミルチャ・エリアーデの影響、その他 Ⅳ 言語を覆す詩人 ――黒岩康「山中智恵子研究」、その他 Ⅴ 「伊勢の闇」とは何か ――富士谷御杖の言霊倒語説 Ⅵ 連作の構造 ――「雨師すなはち帝王にささぐる誄歌」の改作について Ⅶ 「新しいリアリズム」の追求 ――初期から中期に向けての一字空白を含むテクストの考察 Ⅷ 「前定型」への回路 ――中期から最晩年に向けての一字空白を含むテクストの考察 Ⅸ 批評軸としてのクリステヴァ、迢空 Ⅹ あかときやみの歌はあめなるひばりかげ ――『山中智恵子全歌集 下巻』書評 Ⅺ 存在本質の表出 ――晩年の秀歌 Ⅻ 山中智恵子句集『玉すだれ』を読む 13 山中智恵子について語ろう インタビュー(聞き手=「北冬」編集部) 第三章 浜田到論 Ⅰ 言葉の内なる遭遇 Ⅱ 浜田到についてのノート Ⅲ 「死」と「少女」――浜田到のリルケ享受の一側面 Ⅳ 浜田到のリルケ享受についての補記 第四章 塚本邦雄論 Ⅰ 短歌の言葉――塚本邦雄のテクストを中心に Ⅱ 塚本邦雄の一字空白を含む初期テクストについてのメモ Ⅲ 塚本邦雄と北村太郎 Ⅳ 新たな読みの提出 ――塚本邦雄七回忌記念「神變忌シンポジウム」報告記 Ⅴ 構造化からの詩的脱臼は可能か ――リアリティーの本質の隠蔽について 第五章 玉城徹論 Ⅰ 詩的原体験としての松尾芭蕉 ――「連句」と「調べ」の問題を中心に Ⅱ ニヒリズムからの脱却 ――第一歌集『馬の首』の評価をめぐって Ⅲ フィクショナルな劇性 ――第三歌集『樛木』巻頭歌について Ⅳ 歌集を解体する方法 ――自選歌集『汝窯』に関する一、二の感想 Ⅴ やまとうたの心 ――第四歌集『徒行』の構成を中心に Ⅵ どこまでも詩の人 ――印象に残る歌 Ⅶ 白秋と茂吉 ――玉城徹の眼力の恐ろしさ 第六章 言葉のリアリティーの探求 Ⅰ 現代詩としての未来の短歌に向けて Ⅱ 短歌のポエジーとは何か Ⅲ 塚本邦雄・大岡信の方法論争によせて Ⅳ 塚本邦雄『綠色硏究』を中心に Ⅴ 山中智恵子と浜田到 Ⅵ 山中智恵子とヴァレリー、富士谷御杖 おわりに 葛原妙子と山中智恵子 ――存在論的な歌の差異について
-

『万葉集の古代と近代』[内藤明 著]
¥4,180
今日のわたしたちは万葉集をひもとき、額田王や柿本人麻呂ら作者個人の感情表出をそこに読もうとする。だが、それは近代に起きた転倒だった。万葉集においては、人間と自然の、個と集団の、相互性のなかで、さまざまな位相の抒情主体が生成していた。自家中毒を起こしたら、本書を開くとよい。本書がわたしたちを自由にするだろう。 ◇ ここでいう「近代」は、百年余の万葉内部の史における「近代」であり、また万葉集から千数百年を距てた時代としての「近代」の両義を持たせようとしたものである。そして、古代的なるもの、近代的なるものを考えたいと思ったのだが、いかようにとっても近代はとらえがたく、古代や始原への探索は玉葱の皮剥きにも似る。(「あとがき」より) 本書の内容 序 万葉集と現代 Ⅰ うたの構造と様式 第一章 二景対照様式の生成と展開―歌謡・初期万葉・人麻呂歌集 第二章 短歌の二部構造と主体―「見れば……思ほゆ」の型をめぐって 第三章 うたにおける「物」と「思」―人麻呂歌集の寄物陳思歌 Ⅱ 柿本人麻呂作品を読む 第四章 人麻呂歌集七夕歌―七夕歌の生成 第五章 近江荒都歌―構造と位相 第六章 吉野讃歌―歴史と表現 第七章 石見相聞歌―語りと独白 Ⅲ 万葉集の言葉と世界観 第八章 「うつせみ」―讃美と無常 第九章 「みやび」―都市と和歌 第十章 「ますらを」と「たわやめ」―幻想としての性 第十一章 「うれへ」―旅愁と豊饒 高橋虫麻呂の筑波山に登る歌 Ⅳ 万葉集と近代 第十二章 歌人の生成―大伴家持をめぐって 第十三章 万葉集の近代と古代―空穂・茂吉から人麻呂・家持へ 第十四章 「気分」とは何か―窪田空穂と「気分」 Ⅴ 和歌が問いかけるもの 第十五章 うたの始原へ―研究史・和歌の本質と表現 第十六章 和歌・短歌と共同体―うたのゆくえ 四六判ハードカバー376頁 ISBN978-4-86534-354-0 定価 3800円+税
-
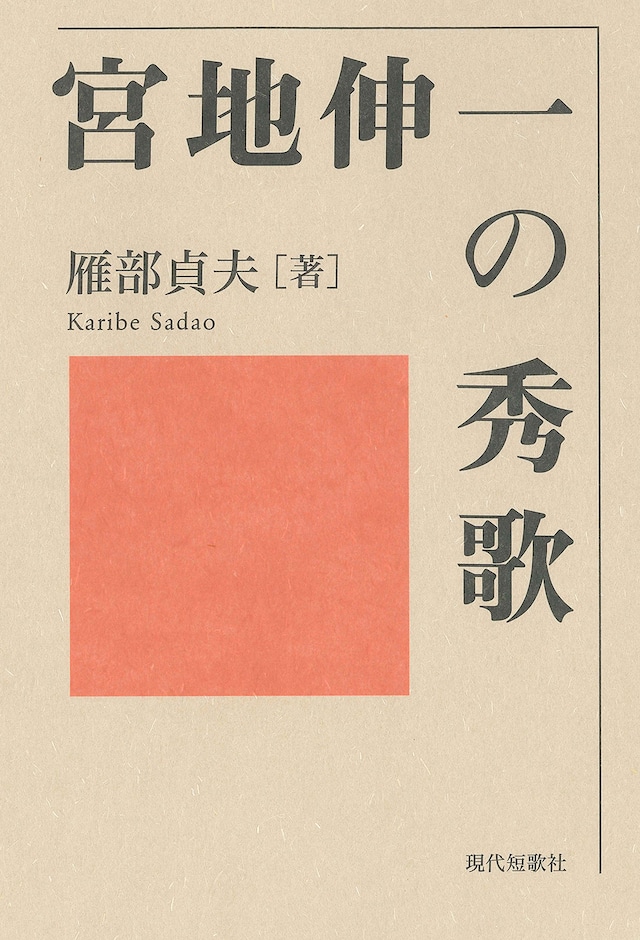
雁部貞夫著『宮地伸一の秀歌』
¥2,860
宮地伸一の秀歌 雁部貞夫/著 アララギ最後の歌人と称すべき宮地伸一の愛弟子だった著者。 宮地の作品世界が凝縮された昭和期の三冊の歌集『町かげの沼』『夏の落葉』『潮差す川』より、 忘れがたい作品を選んで解説、鑑賞。百首選、略年譜を付す。 定価:2,600円(税別) 判型:四六判ソフトカバー 頁数:210頁 ISBN:978-4-86534-328-1 初版:2020年4月24日 発行:現代短歌社 発売:三本木書院
-

横山季由著『アララギの系譜』
¥2,860
アララギの系譜 横山季由/著 「全体について申しますと、非常に下手だ。これがアララギの詠草だといって世間に出せますか」。 土屋文明は亡くなる二年前、歌会でこう慨嘆した。 アララギの唱導した写生とは、リアリズムとは、何だったのか? 子規の改革からアララギ終焉まで、流れ続けた水脈を、豊富な文献を渉猟しつつたどった労作。 定価:2,600円(税別) 判型:四六判ソフトカバー 頁数:286頁 ISBN:978-4-86534-310-6 初版:2020年3月26日 発行:現代短歌社 発売:三本木書院
-
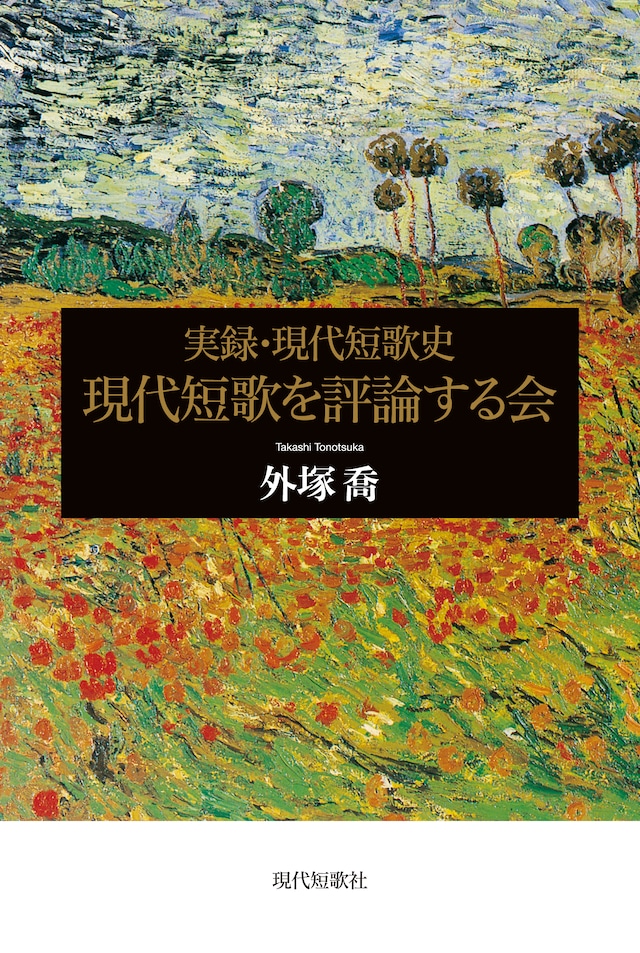
外塚喬著『実録・現代短歌史 現代短歌を評論する会』
¥3,960
片山貞美の差し出した一通の案内状から、その会は始まった。年五回開かれた会合は歌壇ジャーナリズムに一切知らされることがなく、会の発行する「評論通信」もごく限られた者のみに送られた。批評の限りを尽くした歌人たちの肉声をとどめる貴重な記録。 当時の短歌界で華やかに活躍していた歌人に焦点が当てられているわけではない。むしろ、総合誌の巻頭を飾っていたような人の作品を、厳しい目で見ていくことが会としての目的の一つでもあった。(略)誰かが記録として纏めておかなかったら、十年に及ぶ活動が水泡に帰すことは間違いない。事務局を担当した立場上、この仕事は私がしなければという思いが、連載の途中からいっそう強くなった。(「あとがき」より) 書籍データ 定価:3600円(税別) 判型:四六判ハードカバー 頁数:306頁 ISBN:978-4-86534-248-2 初版:2019年3月16日 発行:現代短歌社 発売:三本木書院
-

佐藤佐太郎 純粋短歌の世界[香川哲三/著]
¥3,850
SOLD OUT
第4回(平成28年度)佐藤佐太郎短歌賞 佐藤佐太郎の全13冊の歌集について、作歌の背景や作品世界の深化の足跡をたどり、「純粋短歌」とは何かを具体的かつ平明に解き明かした、歌人佐太郎論の金字塔。 定価:3,500円(税別) 判型:A5判ソフトカバー 頁数:538頁 ISBN:978-4-86534-210-9 初版:2017年7月18日 発行:現代短歌社
-

河野裕子論[大島史洋/著]
¥2,750
第39回(平成28年度)現代短歌大賞 河野裕子の全歌業を辿った、初めての書である。それが、歌人としての河野の出発時から、兄貴のようにいつも近くにいた大島史洋の手になることをとてもうれしく思う。(略)河野の作品が、大島史洋というこれ以上ない読み手を得て、再び読者の目に届くことを、何より喜んでいるのは、河野裕子自身であろう。(永田和宏「帯文」より) 定価:2,500円(税別) 判型:四六判ハードカバー 頁数:233頁 ISBN:978-4-86534-175-1 初版:2016年9月16日 発行:現代短歌社
-

近藤芳美論[大島史洋/著]
¥2,096
戦後歌壇の巨星、近藤芳美に長く師事した著者による評論集。晩年の近藤芳美への貴重なインタビュー、近藤芳美120首選を収録。近藤芳美著作目録、研究書・参考図書・雑誌特集号を附す。 定価:1,905円(税別) 判型:四六判ハードカバー 頁数:224頁 ISBN:978-4-906846-84-9 初版:2013年7月24日 発行:現代短歌社
-

方代を読む[阿木津英/著]
¥2,619
方代の歌は、無名の大衆であることの謳歌である。学問が無くても、エリートにならなくても、金と名誉に縁遠くても、人間として立派に生きていけるのだという自負があり、根づいたものの思想がある。これはマス・メディアの作り出した近代的な〈大衆〉とは似て非なるものであるばかりか、むしろそれをきびしく批判するものである。それゆえに、わたしは方代の歌をこそポスト・モダンと言いたいのである。(「あとがき」より) 定価:2,381円(税別) 判型:四六判ハードカバー 頁数:249頁 ISBN:978-4-906846-20-7 初版:2012年11月1日 発行:現代短歌社
